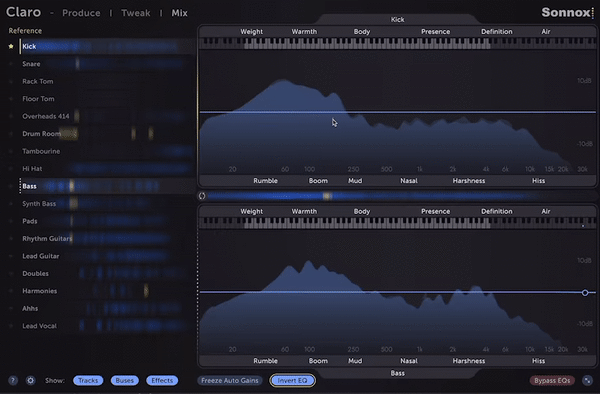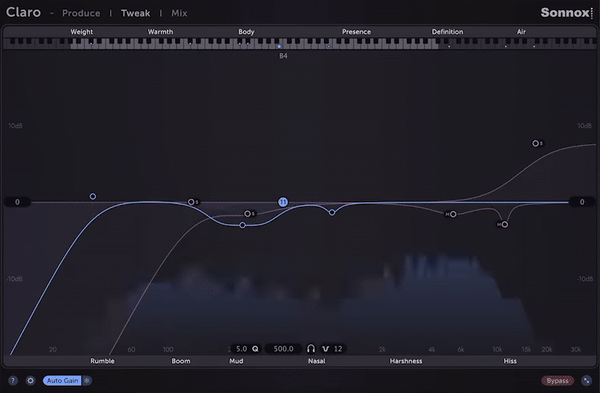【Review】Sonnox「Claro」レビュー(EQプラグイン・機能と使い方・他製品との比較・評価)
メーカーによる一次情情報
Claroは、3つの異なるビューを通じてフォーカスを維持し、ワークフローを加速します。1つ目はPRODUCEビューで、不要な気晴らしや複雑な技術用語を削除しながら、音楽の創造性を積極的に促進する高速でクリエイティブなEQを提供します。次に、TWEAKビューにより、より多くの修正の可能性が開かれ、最もクリーンで最も柔軟なフィルターが提供されます。リアルタイムアナライザーはあなたの動きに適応し、問題のある共振を特定するのに役立ちます。最後に、MIXビューを使用して、ミックスを理解して組み立てます。すべてのトラックが同時に表示され、優先順位を付けたり、相互作用を調べたり、競合するトラック間の周波数の衝突にすばやく対処したりできます。
あなたが寝室のプロデューサーであろうとグラミー賞を受賞したプロであろうと、あなたはあなた自身の音楽的な声を開発するためにコントロールを取りたいと思っています。Claroは、情報に基づいた音楽的決定を独自の直感的な方法で行うことを可能にします。Claroは、コンポジションからファイナルミックスまでの制作プロセスを提供する包括的なEQプラグインであり、3つの異なるビューを備え、泥、乱雑さ、または粗さを防ぐために、より深い洞察と精度を徐々に追加し、トラックをクリアでバランスの取れたミックスにブレンドするのに役立ちます。
特徴
- ClaroのEQは非常に柔軟性があり、26バンドのそれぞれが以下を提供します。
- 愛されているNeveタイプ、それらの最新の派生物、SSL Gシリーズ、および多くのハイエンドのアウトボードイコライザーに似たクリーンで音楽的なサウンドのEQ。
- 左、右、ミッド、サイド、モノラル、またはステレオチャンネル処理により、各トラック内のスペースを修正、拡大、縮小、または作成することができます。
- 20hz〜40kHzの広い範囲。拡張された高周波範囲は、滑らかで風通しの良い品質を提供します-ボーカルやミックスバスに最適です。
- カットフィルターとシェルフフィルターのレゾナンスとオーバーシュートをそれぞれ含む可変Qにより、クラシックなシンセフィルターとハードウェアEQカーブを模倣することができます。
- 外科手術および正確なオーディオバンドの処理のための超急勾配(オクターブあたり120dB)までのすべてのバンド形状の可変スロープ
- Claroのオートメーションは、ほとんどのプレミアムEQとは異なり、スムーズでアーティファクトがありません。
- オートゲインは、信号の内容やEQの選択方法に関係なく、トラックを同じラウドネスに独自に保ちます。
機能と使い方
上記のメーカーのディスクリプションを読んでもピンとこなかったかもしれませんが、Claroはいわゆる通常EQとは少し、異なるコンセプトで設計されているEQです。Claroは3つのUI画面が用意された多角的なアプローチができるEQプラグインです。Produce, Tweak, Mixという3種類の異なるUiが用意されていて、相互に連動しています。まず、トップ画面を見てみましょう。EQというよりエンハンサープラグインのようなUIの印象を受けるかもしれません。この画面では大雑把にEQの設定をしてEQの方向性を決めたり、設定を瞬時に試すのに向いています。具体的には低域、中域、高域の3バンドのEQポイントとハイ、ローカットが用意されています。それぞれの音域がスライダーになっていて、それぞれのEQのゲインを調整できるようになっています。トラックのオーディオ信号は画面上部の簡易的なスペクトルグラムに青く色が表示されて、それぞれの帯域には音の変化(重さ、温かみ、ハーシュネス)などEQ操作によって作用するごく一般的に言われるところ具体的な音色の性格が記載されているので、非常に感覚的に操作できるようになっています。例えば、サウンドに重みが足りないからこの帯域を操作したいなど。
EQの周波数は上のアナライザーで表示された数字のボタンを動かすことで移動できます。便利なことに、それぞれの丸いスライダーをポイントするといわゆるそれぞれの楽器全般に対して重要なEQポイント例えば低域の場合(20, 40, 70, 100,150など)が表示されるのでそれを押すことで瞬時にその帯域に設定可能。後述しますが、これらの設定はTweakで表示されるごく一般的なEQ画面に連動してして、それに応じてEQポイントが自動的に設定されます。つまり、EQをいちいち設定する前にざっくり置くことができるということですね。複雑な操作をする場合こちらから入ると逆に手間になる可能性もありますが、この画面の操作でしっくりくる設定になってしまうということもあると思います。こちらの操作の方が楽と感じる人もいるでしょう。
同様の操作でステレオ操作もできます。これは実際の操作としてはM/SスプリットEQのサイド信号の処理でこちらも同様にEQ画面にサイドEQのポイントが設定されます。仕組みから察するかと思いますが、細かな操作ができるわけではなく、その操作ではステレオ操作が解決しないこともありますが、ちょこっとサイドをいじりたいといった時に結構便利。M/S分離のEQはEQポイントが増えて設定に時間がかかることもあるので。
上記操作で解決しない場合Tweakという微調整モードに移ります。おなじみのEQ画面が表示されます。EQポイントを選択し表示するとEQタイプがポップアップされ一般的なEQの種類から選ぶことができます。EQカーブとしてはNeve、SSL GなどアナログEQにインスパイアされたカーブと挙動が反映されています。(それぞれの形状についてバリエーションは1つでアナログモデルからEQタイプをそれぞれ選べるわけではないので注意。)
アナログEQにインスパイアされているということですが、Q幅だけでなく、ベルの勾配も細かく調整できるのでなかなか器用に操作できます。
スプリットでLR、MSのEQをそれぞれ表示して分離して操作をすることができます。ピアノ画面でEQポイントの位置が点で表示されるので12音階でのピッチと相互に確認できます。これはおなじみかもしれませんね。また、EQ調整によるゲインの変化を原音と一致させるオートゲインモードも用意されています。
それぞれのEQポイントだけをListenモードで聴くこともできます。
3つ目の画面はMixということでそれぞれのトラックにClaroをインサートすると自動的にそれらを認識し、一つのEQ画面でそれぞれのEQ設定をいじることができます。これはsonible「smart:EQ 4」の先駆けともいえる機能。いちいちそれぞれのEQにアクセスせずに一つの画面で調整できるわけですね。2つのEQ画面を並列して比較することができ、実際には比べる際にメイントラックともう一つのトラックの2つのインスタンスを比べることができます。画面左、それぞれの周波数の分布がスペクトルグラムで表示され、2つの周波数信号を合わせた分布も表示されるため(多い部分は色が濃く表示されます。)周波数の被りを一目でみて調整することで問題のあるマスキングに対して処理をすることができるわけです。これはユニークな機能ですが、互換性のあるDAWに対して通常のトラック、バストラック、エフェクトトラックをそれぞれ認識して分類するので下のそれぞれのボタンを押すことでバストラックだけを絞ったりすることができます。それぞれのトラックのEQの設定を逆転させることもできます。
他製品との比較
まず比較する前に製品のEQの挙動や精度を検証する上で留意しておきたいのが、それぞれのEQカーブの挙動です。アナログ由来とのことですが、
例えば、Produce画面で単純にデフォルト設定でそれぞれのEQポイントをスイープしてみるとわかりますが、単純にベルの形状でEQが動くのはなく、周波数ごとにEQカーブの形状が変化します。これはEQモデリングではおなじみかもしれませんね。HighのEQポイントを左右にスイープして操作すると(UI上のGainは一定です)ちょうど上に凸の放物線を描くようにEQポイントの高さが変化し、左右の裾も左右線対称ではありません。要は様々なアナログハードウェアをモデルに良い感じの音が維持できるようにカーブの挙動が設計されているわけであります。
音質に関して、試しにClaroとThree-Body Technology「Kirchhoff-EQ」の様々なモードで測定上のEQカーブをできるだけClaroにできるだけ近似させて、比較してみましたが、モードによって、あるいはアコースティックピアノなど楽器によってはKirchhoff-EQの方が低域の解像度や高域の自然なEQ感が若干良く聞こえる場面もありましたが、いくつかのシンセサウンドなどを比較すると多くの人が誤差の範疇と考えるくらいにはほとんど違いがないと感じるものも多くありました。トランジェントも聴覚上の有意性のある大きな差異はそこまで気にならない印象。少なくとも比較して大きな品質の差を感じるほどのものではなく、一定の品質の高さを言及することができると思います。ドラムに関しても高域でKirchhoff-EQの方が若干自然さがより感じられるかどうかなという印象。注意深く聞かないとほとんど違いがわからないという方もいるのではないかと思います。他のEQとの比較検証も機会があればしてみたいところです。また、Kirchhoff-EQと最小位相モードとの比較だとほとんど位相歪みの差異もありません。Kirchhoff-EQと違ってClaroにはダイナミックEQ(あちらの看板機能のひとつ)がないです。
評価
製品のアプローチとしては非常に面白い視点から設計されていると評価できます。EQで最初にポイントを打つのではなく、スライダーで各帯域にエフェクト量を調整する感覚でゲインをいじるというのはわかりやすいと感じる人もいるでしょう。その後にEQ画面で細かく調整を加えるということなのでEQに慣れていない人がEQの操作にスムーズに慣れて移行する上でも良い設計と鳴っているかもしれません。周波数の表示とともに周波数ごとの性格やBoom、ヒスノイズなどの問題も記載してあるので闇雲にEQをいじりがちな方にとっては割と親切設計かもしれません。かといってEQをAIに自動お任せといった放り投げるタイプのプラグインではなく、ほとんどマニュアル操作を要求するプラグインでもあります。全自動で放り投げたい方には最適解ではありません。他のEQにも備わっていたりしますが、オートゲインのおかげで見せかけのオーディオの変化に惑わされなくなります。
周波数被りに関しても、自動で調整するのではなく、被りを表示してくれる(UIの配置が非常に合理的でみやすい)といったように最終的には自分で判断することを要求している点においても意外に堅実なプラグイン。音質に関しても大きな文句はあまりないと感じ、一定の品質がみられます。
プリセットはないと思われます。(少なくともデフォルトではインストールになく未確認です。)肝心のEQ画面の操作性は特に便利というところはあまり感じませんでした。
上述のEQ挙動と比較から一定の音質の評価はできるかと思われます。
EQの種類はM/S対応しており、一通りそろっていますが、Kirchhoff-EQのようにEQモデルのタイプから選べるといったオプションはありません。筆者としては他のプラグインとの差別化としてProduceとTweakの2画面操作という多角的アプローチの設計を挙げておきたいところで非常にユニークで使いやすいと思います。マニアックな追い込みの機能があるというわけでなはいないので現在のマスタリング水準のこれまでにない精度の最新機能や圧倒的な多機能性を求めるマニアックな人にとっては物足りないと感じるかもしれません。機能を詰め込むのではなく、洗練された合理的なUI設計というところにこのプラグインの強みがあり、一定の品質を評価した前提で実用性に目を向けるのであればエンジニアリングに特化された方よりもむしろより作曲家やプロデューサー向けの設計といえるかもしれません。